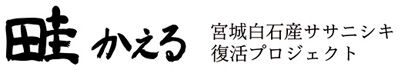儀式や風習、日々の生活様式に深く関わる米

緑生い茂り、折々に自然の移り変わりを見せてくれる益岡公園内。かつての白石城二の丸跡、まちの歴史と共に時を刻んできた「白石神明社」を訪れました。創建は古く大同2年(807)。本来は白石の別の地に鎮座していましたが、度重なる大火により明治33年に現在の益岡町に移転。天照大神を主祭神とし、仙台藩主伊達政宗公と白石城主片倉景綱公が合祀されており、市内外から参拝客が訪れます。代々宮司を務める佐藤家も、かつては片倉家の家臣。人々の生活に寄り添い、その役割を果たしてきた神社です。
今回は、古来から人の暮らしと結びついてきた米と神事について、白石神明社禰宜の佐藤文比古さんにお話を伺いました。

古い神社建築様式の一つ「神明造」の社殿。奥行きより幅が大きく、弥生時代に穀物をおさめた「高床式倉庫」から神宝を納めるよう発展したものといわれる。その代表とされる伊勢神宮は「唯一神明造」といわれ、厳格な神明造のため他社で同一のものは造れない。
古くは縄文時代にさかのぼる米づくり。中国から九州へ伝わった稲作技術は弥生時代にかけて東へと伝わりました。米づくりは営みの中心となり、人々は米がたくさん獲れることを祈願し、無事収穫できた米を神に献げ、米をいただくことに感謝して暮らしてきました。
「神道では米は一番大切な供物です」開口一番、佐藤さんはおっしゃいます。どのような神事でも、まず第一に米を捧げる。酒や餅といった米の副産物も神への尊い供物です。
一年の歳時と関わるように、神社において執り行われる儀式や伝統行事。白石神明社では、【祈年祭:2月17日】【春季例祭:4月15日】【秋季例祭:10月16日】【新嘗祭:11月23日】を主な大祭として、大小数々の神事があります。特に早春の「祈年祭」や「春季例祭」、晩秋の「新嘗祭」は米や農作物と深い関わりがあり、氏子の皆さんと一年の五穀豊穣と安全を祈願し、収穫に感謝する大切な神事。日本では飛鳥時代に始まったといわれる「新嘗祭」では、こちらの白石神明社でも氏子の皆さんから新米が捧げられ、一年を通して神殿へ供えられます。
「お下げした後に、家族でありがたくいただきます」と、神職に携わる者として常に米や氏子の皆さんへの感謝を忘れないと話す佐藤さん。食事の基本はやはり「ご飯」だそうです。毎日当たり前にいただくご飯はありがたいもの。「米一粒残すな」と食卓で親に言われた世代、どんな炊き上がりでも日本の米は美味しいと話していらっしゃいました。

白石神明社禰宜の佐藤文比古さん
「日本人はお米をいただいている民族です。神事を通して地域の皆様へご奉仕する者として、歳時と神事のつながりや日本の奥ゆかしい伝統文化など、再認識のきっかけにしていただければ……米などの農産物に感謝しながら、このプロジェクトを応援しています」最後に、佐藤文比古さんからメッセージをいただきました。
日本人にとって「米」とは単なる食べ物ではなく、長い歴史の中で暮らしと関わってきた特別な存在。人生の節目を迎える毎に神社を参拝する習慣も、日本人の心に根付く良き慣習です。そこには常に米が神への供物として存在してきました。
お宮参りや七五三、合格祈願や結婚式など、人の成長にも寄り添う白石神明社さん。家内安全や厄祓い、交通安全や商売繁盛などのご祈祷にも一年を通してご奉仕されています。益岡公園内、散策の折にはどうぞお立ち寄りください。

【白石神明社】
宮城県白石市益岡町1−17
0224-25-1180
http://shinmeisya.sakura.ne.jp
最新情報をお届けします